投資を始めるなら必ず押さえておきたいお金の常識

株式市場への初めての一歩は、不安と期待が入り混じりますよね。そこで登場するのが、今回ご説明する「投資信託」。分散投資やプロの管理など数々の魅力がありますが、その一方で元本割れや手数料のリスクも潜んでいます。果たして、投資信託は未知なる冒険か、確かな資産形成への近道か。今回は、そのメリットとデメリットに迫ります。
投資信託とは
「投資信託」とは、専門家が投資家のお金を集め、その資金を株式や債券などに分散投資して運用する仕組みです。つまり、みんなで力を合わせて一つの大きな資金を作り、専門の人が賢く運用してくれるんです。運用の成果は、各投資家に分配されます。
ただし、運用は市場の状況に左右され、利益が出たり損をすることもあります。投資信託は元本が保証されていないため、損失の可能性もあることを覚えておきましょう。銀行の預金とは異なり、リスクがあるけれども、適切に利用すれば将来の資産形成に役立つ魅力があるんです。

◻️4つのメリット
1. 分散投資
投資信託は、異なる種類の資産を組み合わせてポートフォリオを構築することができます。これにより、単一の投資先に依存せず、例えば株式、債券、不動産など異なる資産クラスに分散投資が可能です。たとえば、ある企業の株価が下落しても、他の資産クラスが利益をもたらすことで全体のリスクが軽減されます。この分散投資の仕組みにより、投資家は単一の市場変動に影響を受けず、安定した収益を期待できます。これはリスクヘッジの観点からも有益であり、市場の変動によるポートフォリオ全体の影響を最小限に抑えることができます。
2. プロによる運用管理
投資信託はプロのファンドマネージャーにより運用管理が行われます。これは、経験豊かで市場に精通したプロフェッショナルが、投資信託の資産を効果的に監視し、市場の変動に適応することを意味します。例えば、好況時には成長性の高い銘柄に重点を置き、景気後退時には安定性のある資産にシフトするなど、様々な市場状況に対応します。一般の投資家はこれらのプロの戦略を活かし、専門的な判断を頼りにすることができます。また、ファンドマネージャーは継続的に市場動向をモニタリングし、最適な投資先を選定するため、投資家は日々の市場の変動に対処する手間を省くことができます。プロの管理により、一般の投資家も市場のプロフェッショナルと同等の手腕を享受できるのです。
3. 高い透明性
透明性が高いことも魅力の一つと言えるでしょう。これは、毎日、取引価格である基準価額が公表され、資産価値や値動きが投資家にとって分かりやすいという点にあります。イメージとして、これは魔法瓶が透明で、いつでも中身が確認できるようなもの。投資信託も同様に、その日の基準価額が公開されることで、投資家は自分のポートフォリオの状態をリアルタイムでチェックできるんです。さらに、定期的な監査を受けているため、信頼性も高まっています。これによって投資家は、適切な情報をもとに冷静な判断ができ、投資の透明性と信頼性がしっかりと保たれているといえるでしょう。
基準価額とは?
基準価額は、投資信託において一口あたりの値段を指します。これは、ファンド全体の資産を総額の口数で割った値で、日々の市場動向によって変動します。基準価額が上がれば一口あたりの価値が増し、下がれば逆に減少します。
4. 少額からの投資が可能
また、少ない資金から投資ができるので、まとまった軍資金がない人でもチャレンジできます。通常、株式や債券に投資するには相応の資金が必要ですが、投資信託では1万円程度から手軽にスタートできます。少額からでも投資の世界に足を踏み入れ、資産形成の第一歩を踏み出すことができるんです。この手軽さが、初めて投資に挑戦する人や資産を少しずつ積み立てたい人にとって魅力的な点です。大金を用意する必要がなく、自分のペースで投資を進めることができます。
◻️3つのデメリット
1. 元本割れのリスク
投資信託におけるデメリットの1つ目は、「元本割れ」です。元本割れとは、さまざまな理由で当初投じた投資金額を下回ってしまうことです。例えば、投資家が購入した時点で元本が減少する状況があります。これは、投資信託を1万円で購入した場合、初めにかかる手数料により、実際の投資金額は1万円未満となります。仮に手数料が1%であれば、投資額は1万円 – (1万円 × 1%) = 9,900円となります。
さらに、市場の変動により基準価額が下落した場合、投資家の元本も減少します。例えば、基準価額が5%下落した場合、元本は9,900円 × (1 – 5%) = 9,405円となり、元本割れが発生します。このように、手数料と市場の変動の影響で、投資家は最初から元本を割る可能性があるため注意が必要です。
2. 手数料や税金による利益の圧縮
また、手数料や税金によって最終的に手元に残るお金が減少します。具体的な例を挙げて説明します。例えば、投資初心者が1万円の資金で投資信託を購入する場合、購入時にかかる申込手数料が2%だとすると、手数料分だけ元本割れが生じます。計算すると、購入額は1万円 × (1 – 2%) = 9,800円となります。
その後、投資信託を保有する期間中にかかる信託報酬も利益を圧縮します。仮に年間の信託報酬が1%なら、1万円の資産の年間の手数料は1万円 × 1% = 100円です。これが資産から差し引かれ、実際の利益はその分減少します。
解約時にかかる信託財産留保額も考慮すべきです。現在ではノーロードファンド(手数料無料のファンド)も増え、信託財産留保額のないファンドも一般的ですが、一部にはまだ存在することもあります。
さらに、これらの手数料を差し引いて得られた利益に税金がかかります。たとえば、一般の投資家が得た利益には、税率20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)がかかります。ただし、一般NISAやつみたてNISAなどを活用した場合、特定の条件を満たす限り、利益は非課税となります。
信託報酬とは?
投資信託を管理するための費用で、投資家が保有中に毎日一定の割合で差し引かれる手数料です。一般的には、信託財産の中から「純資産総額に対して年0.5~2.0%程度」です。簡単に言えば、プロに資産を預けて運用してもらう対価です。信託財産留保額とは?
投資信託を解約する際に投資家が支払う費用のことです。一般的には、基準価額に対して3%程度ですが、差し引かれない投資信託も多くあります。
3. タイムリーな売買ができない
「タイムリーな売買が難しい」という点もデメリットになり得る可能性があります。通常の株式取引とは異なり、投資信託は価格が刻々と変動する中で即座に取引することができません。この制約は「ブラインド方式」として知られ、基準価額が未知の状態での売買注文を許容します。
例えば、基準価額が毎晩確定すると仮定しましょう。朝に投資信託を売りたくても(=約定)、その瞬間の基準価額が分からないため、実際の取引ができるのは基準価額の確定後となります(※)。このタイムラグが、市場の急変や重要な情報に素早く対応できない状況を招く可能性があります。
(※)約定にかかる日数はファンド毎に異なり、一般的には、海外市場に投資(運用)するファンドは申込の翌営業日、国内市場に投資(運用)するファンドは申込の当日が約定日となります。
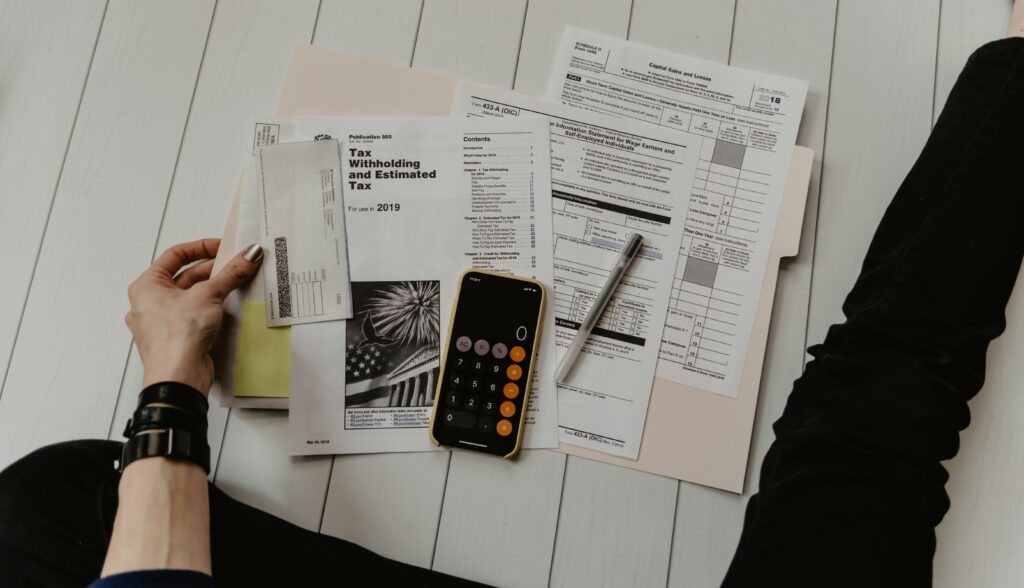
いかがでしたでしょうか。
投資信託は、資産を分散し、プロの手で運用されるメリットがあります。透明性も高く、少額からスタートでき、これらは確かな資産形成の一翼を担います。しかし、慎重に。元本割れや手数料、税金といったデメリットも見逃せません。冷静な判断と知識を身につけ、未来の投資への第一歩を踏み出しましょう。

コメントを残す